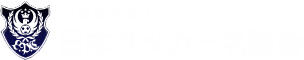特別記事|「SHUKYU」文化から見つめるスポーツのかたち

2015年に雑誌『SHUKYU』を創刊して以来、サッカーを文化のまなざしから捉え、読むこと、語ること、着ることとしてその側面を描き出してきた大神崇さん。雑誌から始まったその活動は、しだいにグッズ、イベント、空間へと広がっていった。フットボールを社会と文化の視点から掘り下げ、「サッカーを日常にする」ことを追求するその思考は、今、千駄ヶ谷の小さな店舗「4BFC」に結実している。
単なるメディア運営にとどまらず、「場所づくり」「記録としての紙」「日常に溶け込むアパレル」へと活動が横断していく中で、大神さんはどんな思考を積み重ねてきたのか。社会と文化、サッカーと日常の狭間を縫うように活動を続けてきたその足跡を辿ってみたい。
Edit & Photo:Shogo SATO
「SHUKYU」創刊ー雑誌から始まる文化の立ち上げ
「『SHUKYU』は2015年に最初の雑誌という形からスタートしました。それまでサッカーの仕事をしていたわけではなくて。イベントの企画とか文化系のことをやっていて、サッカーを違う角度から見られないかと思ったのがきっかけです。」
サッカーを意味する日本語「蹴球」。それをアルファベット表記で『SHUKYU』とすることで、独自の響きと認知をつくり出した。若い世代にはなじみがない言葉だが、だからこそ興味を持たれる。「意味は伝わるし、響きとしてもアルファベットにしたときのバランスが良かった」と大神さんは語る。
雑誌では選手だけでなく、サポーター、セレクトショップ、サッカー英語講師、デザイナーなど、サッカーの周縁にいる人々の声を取り上げてきた。表紙に代表選手を起用する号もあれば、海外のインディーな人物を特集する号もある。「どちらにも優劣をつけたくない」というスタンスがある。
「サッカーを中心に据えつつも、その周りにある文化や人間関係をどう描くかがテーマでした。いろんなものをフラットに見せること。ページレイアウトや写真配置も含めて、そこは意識しています」
1993年当時のJリーグユニフォームやグッズ、日本サッカーミュージアムに展示されているアイテムを丁寧に撮影・掲載した号もあり、資料的価値のある雑誌としても評価されている。

拡張する『SHUKYU』のクリエイティブ
『SHUKYU』として活動を続ける中で、プロダクション的な依頼も増えていった。メーカーやブランドの新作プロダクトが出るタイミングで、プロモーション用のスチールや映像の制作を任されることが多くなった。
「モデルを使っての撮影が中心です。サッカーというよりはファッションの文脈でビジュアルを作ることが多いですね。」
Y-3と日本代表のコラボユニフォームのビジュアル制作も担当した。中でも印象的だったのが、2006 FIFAワールドカップ ドイツ大会の公式球“チームガイスト”の復刻プロジェクト。世界中のビッグクラブと連動したプロモーションで、グローバル向けの撮影を『SHUKYU』が担当することになったという。
「日本で撮影することになった流れでなぜかうちに任されて(笑)。あれは大きな仕事でしたね。」
雑誌の一部号では英訳を掲載し、Instagramも海外向けの発信を意識して運用している。「日本のサッカーメディアで英語併記をしているところは少ない。ニッチなテーマでも海外に届ければ、ニッチ自体が拡大していく。」そんな逆転現象が、確実に起きているという。

Jリーグを"着る" ー記憶の入り口としてのロゴとグッズ
Jリーグ30周年を契機に、SHUKYUでは記念グッズを制作した。Jリーグとのライセンス契約を正式に結び、リーグロゴを使用したプロダクトを展開している。
「開幕当初に流行った“カテゴリー1”のような、シンプルでロゴが主役のグッズが好きなんです。どのクラブのサポーターでも手に取りやすい。」
特に国立競技場はホームクラブを持たないスタジアム。だからこそ、リーグのロゴは“中立”な記号として機能する。実際、スタジアム帰りや海外からの観光客が購入するケースも多く、現在はKAMOスポーツでも取り扱われている。
Jリーグのロゴは1993年から基本的にデザイン変更がない。フラットデザインとして今も通用する普遍性があり、「90年代っぽさ」が今は“エモい”として再評価されてもいる。
「ロゴやエンブレムって“記憶の入り口”になるんですよ。その時代、その選手、その空気感を思い出させてくれる。そういう記号を使ったグッズが作りたい。」
「いくらコンセプトが良くても、自分が着たいと思えないものは作らない。SHUKYUのグッズは“自分がほしいから作った”という側面が強いですね。」

千駄ヶ谷から世界へー場所と人の交差点「4BFC」
『SHUKYU』から生まれた活動は、東京・千駄ヶ谷にある拠点「4BFC」という空間に発展した。看板のないそのビルの一室に、SHUKYU(雑誌)、BENE(古着)、Football & English(語学)、CITY BOYS FC(デザインクリエイティブ)の4人のメンバーが関わっている。
それぞれ異なる立場からサッカーと接続するクリエイターたちだ。
「みんなサッカーとの関わり方が違うけど、共通して“日常にサッカーがある”という感覚を持ってる。あえて違う人と空間をシェアすることが、この場所の多様性になっていると思います。」
BENEは主に海外で古着を買い付けており、セレクトには強いこだわりがある。「基本的にセレクトアイテムは現地買付けです。他の店とはちょっと違う視点があると思います。」
週末のみの営業だが、海外からの来訪者も多い。
「オープン当初から、海外のお客さんがすごく多かった。英語併記でインスタを発信していたこともあって、“SHUKYUは知らないけど4BFCは知ってる”という人も増えています。」
“ニッチな活動”がそのまま拡大している、そんな実感があるという。


サッカーが”語られる場所”を作るということ
雑誌、グッズ、空間と活動を広げてきた『SHUKYU』だが、その根底には「サッカーを日常にする」という信念がある。
「“サッカー=プレイヤーかサポーター”という構図が強い。でも、“語る・飾る・着る・つくる”といった文化的な関わり方ももっとあっていいと思う。」
大神さんが描く理想は、カフェのようにフラッと寄れて、本を読んだりコーヒーを飲んだり、隣でボールも蹴れる、そんな空間だ。
「現実的には簡単じゃないけど、いつかそういう場所が持てたらいい。まずは雑誌を続けていくことが基盤。SNSは流れるけど、紙やモノは残る。10年後、“この時代の空気がある”と思えるものを残していきたいんです。」

LINK
大神 崇 / Takashi Ogami
Planner / Editor / Writer
The founder and editor in chief of SHUKYU Magazine.
1984年大阪生まれ。神戸大学経営学部卒業。
フットボールカルチャーマガジン「SHUKYU Magazine」編集長。
原宿のオルタナティブスペース「VACANT」創設に携わる。2016年独立。
カルチャーからスポーツまで、ジャンルにとらわれない活動をしている。
SHUKYU Magazine >> https://shukyumagazine.com/
SHUKYU Instagram
SHUKYU Facebook
SHUKYU X